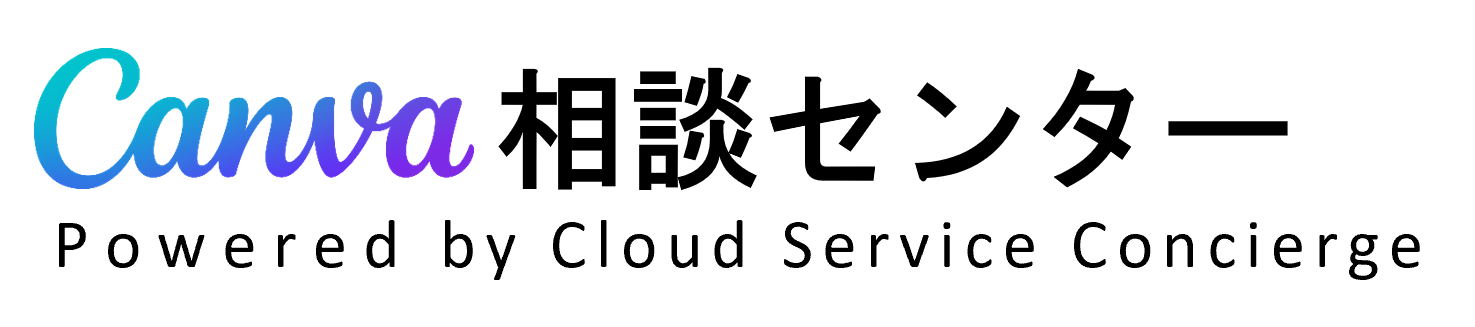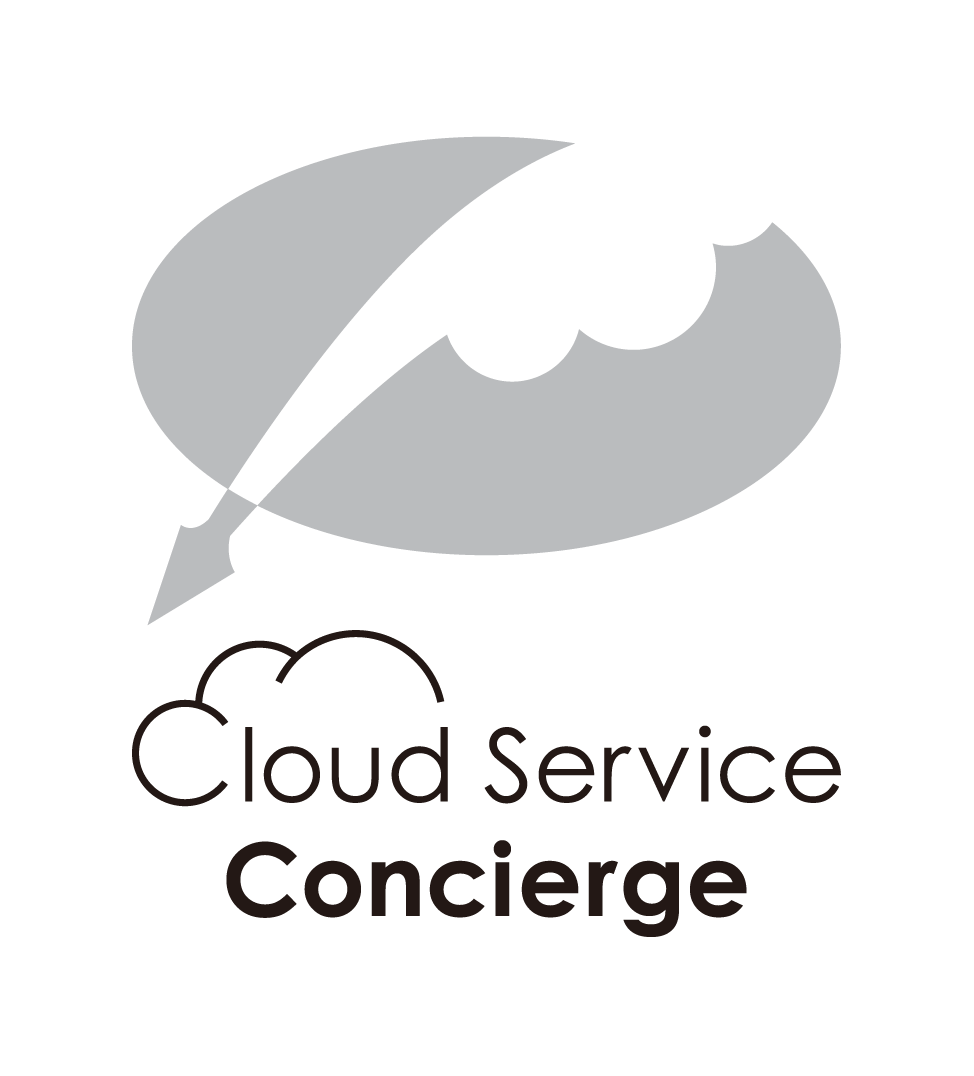デザインの外注と内製、どちらにするべき?メリット・デメリット、判断すべきポイントについて解説
ビジネスにおけるデザインは、企業の顔とも言える重要な要素です。では、デザイン制作を外部の専門家に依頼する「外注」、デザインを社内で制作する「内製」、どちらが自社にとって最適なのでしょうか。
外注では専門性の高いデザイナーによる質の高い成果物が期待できる一方で、内製には、社内コミュニケーションの円滑化や迅速な対応といったメリットがあります。しかし、どちらを選ぶにせよ、自社のニーズを明確にし、目的に合った方法を選ぶことが重要です。
この記事では、デザインの外注と内製、それぞれのメリット・デメリットを徹底比較し、自社にとって最適な選択をするためのポイントを解説します。
以下の記事では、 “制作物100%内製”を実現した企業さまの導入事例をご紹介しています。
⇒ Canvaで業務はここまで変わる!“制作物100%内製”を実現した導入事例
目次[非表示]
- 1.デザイン外注のメリット
- 1.1.成果物のクオリティーの担保
- 1.2.社内リソースを効率的に活用できる
- 1.3.外部の客観的な視点を得られる
- 1.4.必要な分だけの予算に抑えられる
- 2.デザイン外注のデメリット
- 2.1.納品までに時間がかることがある
- 2.2.コミュニケーションコストがかかる
- 2.3.制作費用が膨らむ可能性がある
- 2.4.情報漏洩リスクに注意が必要
- 3.デザイン内製のメリット
- 3.1.スムーズなコミュニケーションが可能
- 3.2.ノウハウやスキルが社内に蓄積する
- 3.3.急なスケジュール変更にも対応しやすい
- 3.4.コストが安定しやすい
- 4.デザイン内製のデメリット
- 4.1.成果物の品質が担当者に依存する
- 4.2.スキル向上に時間がかかる
- 4.3.固定費が発生する
- 4.4.デザイナー採用・確保の難しさ
- 5.外注と内製で迷った際の判断ポイント
- 5.1.コストをどう考えるか
- 5.2.納期に求める柔軟性
- 5.3.案件数と社内リソースのバランス
- 6.まとめ
デザイン外注のメリット
デザイン業務の依頼方法は、外部の制作会社やフリーランスのデザイナーに依頼する「外注」か、社内デザイナー(インハウスデザイナー)に依頼する「内製」かの2つの選択肢があります。
社内デザイナーは、自社製品・サービスの継続的な改善やブランドイメージの維持に強みを発揮します。一方、外部デザイナーは、多様な業界との協業経験から、幅広いデザインスキルと客観的な視点を提供できます。
どちらを選ぶかは、自社のニーズや目的、予算、求めるスピード感などによって異なります。それぞれの特性を理解し、最適なパートナーを選択することが大切です。
まず、デザイン外注のメリットから見ていきましょう。
成果物のクオリティーの担保
デザイン外注のメリットの一つは、成果物のクオリティーを担保できる点です。専門のデザイナーは、豊富な経験と実績に基づいた、高品質なデザインを提供する能力に優れています。特に、複雑なプロジェクトやブランドイメージの向上を目的とする場合、こうしたプロのスキルが非常に役立ちます。外注を活用することで、社内では得られない新たな視点や創造的な提案を受けることができ、その結果、より洗練された成果物を生み出すことができます。
プロのデザイナーが持つ確かな技術は、顧客やターゲット市場に適切なイメージを届ける上で欠かせない要素と言えるでしょう。
社内リソースを効率的に活用できる
外注することで社内リソースを効率的に活用できる点は、企業にとって大きなメリットです。特にデザイナーを外部に依頼する場合、デザインに特化したタスクをプロフェッショナルに任せられるため、内部のチームは自社独自のコア業務に集中できます。このような分業体制により、各メンバーが専門性を最大限発揮できるだけでなく、社内全体の生産性向上にも寄与します。
さらに、重要なプロジェクトの進行中や繁忙期には、外注の柔軟な対応能力が重宝されます。他のプロジェクトへの影響を最小限に抑えながら、効果的なリソース配分が実現し、継続的な成長を目指しやすくなります。
このように、デザインの外注は効率的な業務遂行に役立つだけでなく、戦略的な社内リソースの活用もサポートします。
外部の客観的な視点を得られる
外注には、外部の客観的な視点を得られるという大きなメリットがあります。外部のクリエイターは、社内のスタッフに比べてより中立的で偏りのない視点からデザインを提案することが可能です。この中立的な視点によって、企業内部では気づきにくい新しい発見や独自のインサイトを引き出し、予期しない価値を生むことも少なくありません。
また、外部のデザイナーは多くの場合、異なる業界での経験や多様な背景を持っています。このような多様な知識や視点をプロジェクトに取り入れることで、独創的で画期的なアイデアが生み出される可能性が広がります。
結果的に、製品やサービスが従来よりも広範囲のターゲット層にアプローチできるようになり、競争力のあるデザイン戦略を実現するための大きな助けとなるでしょう。
必要な分だけの予算に抑えられる
外注によるメリットの一つとして、必要な分だけの予算に抑えられる点も挙げられます。プロジェクトによって発生するコストを事前に明確に見積もることができるため、無駄な支出を最小限にすることが可能です。例えば、デザイナーをプロジェクト単位で外注する場合、その都度必要な業務量に応じて依頼を調整できるため、特に短期間のプロジェクトや特定のキャンペーンにおいて効果的なコスト管理が実現します。
また、外注による柔軟な予算管理は、ビジネス全体の財務戦略の最適化にも寄与します。これにより、必要なリソースを効率よく活用しつつ、高品質な成果を得ることができます。
デザイン外注のデメリット
デザインの外注にはさまざまなメリットがある一方で、デメリットも無視できません。
以下では、デザイン外注の具体的なデメリットを解説します。
納品までに時間がかることがある
外注したデザイン案件では、納品までに時間がかかることがしばしば見受けられます。これは社外のデザイナーが多忙なときや、別のプロジェクトの優先順位が高い場合に納期が遅れる可能性があるためです。。
さらに、プロジェクトの進行には密なコミュニケーションが必要な場合が多く、双方のスケジュールを調整するために時間を要することがプロジェクト全体のスケジュールに影響を与える要因となります。特にデザイナーとの連携不足や確認作業の遅れは、スケジュールの進行を妨げることがあります。
納期が遅延すると、成果物を活用したマーケティングの実施やクライアントへの重要な提案にも悪影響を及ぼす可能性があるため、最初の段階でデザイナーとの適切なスケジュール共有や進捗管理が必要です。これにより、リスクを最小限に抑え、プロジェクトの成功に繋げることができます。
コミュニケーションコストがかかる
外注を利用する際、コミュニケーションコストが発生することは避けられません。特に、デザイナーとの情報共有や進捗確認においては、多くの時間と労力を費やす場面が頻繁にあります。
この工程では、具体的な要件や意図を正確に伝えることが非常に重要ですが、それが難しい場合には解釈のズレが生じ、細かな修正が必要になることが一般的です。結果として、無駄なやり取りが増え、作業スピードの遅延に結びついてしまうことも珍しくありません。
これを防ぐためには、デザイナーに対して明確な指示や適切で具体的なフィードバックを行うことが重要ですが、それ自体がさらなる手間を伴う点は考慮する必要があります。
制作費用が膨らむ可能性がある
外注によるデザインプロセスでは、制作費用が膨らむ可能性が存在します。クオリティーを求める中でデザイナーとのやり取りが増えることにより、想定以上のコストが発生することがあります。そのため、予算通りに収めることが難しい場面も少なくありません。
初期段階で見積もりを提示されることが一般的ですが、デザイン修正の回数増加や追加のリクエストが重なることで、結果的に費用が大幅に上昇するケースは避けられないことがあります。こうした状況では、デザイナーの提案や対応によりプロジェクト全体の方向性が変わる場面もあるため、事前の計画と予算管理が重要です。
これにより、プロジェクト全体のコストが想定より高くなる可能性があり、特に小規模な企業にとっては資金計画への影響が大きくなります。デザイナーとの効果的なコミュニケーションを行いながら、予算内で成果物を完成させるための計画を立てることが肝要です。
情報漏洩リスクに注意が必要
デザインを外注する際には、情報漏洩リスクに対する注意を怠ることはできません。外部のデザイナーに機密情報や内部資料を共有する場合、それらの取り扱いに細心の注意を払う必要があります。不適切な管理や情報が社外に流出してしまうことで、企業にとって重大な損失をもたらす結果となる可能性があります。
特に、セキュリティ対策が不十分なデザイナーや外部業者を選ぶことは、企業にとって潜在的なリスク要因となります。そのため、デザイナーを選定する際は、技術力だけでなく、安全な情報管理ができる信頼性を持つパートナーであるかを確認することが重要です。
情報漏洩リスクを軽減するための具体的な手段としては、機密保持契約(NDA)の締結が挙げられます。この契約を通じて情報の取り扱いに関するルールを明確化し、万が一のリスクを最小限に抑える取り組みを行うべきです。また、情報を共有する範囲や量を必要最小限に制限し、デザイナーと透明性の高いコミュニケーションを心がけることも大切です。
デザイナーと円滑に連携する一方で、情報管理に関する意識を高め、リスクを未然に防ぐことで安心して外注を進めることができるでしょう。
デザイン内製のメリット
デザインの内製化には、企業にとって多岐にわたるメリットがあります。スムーズなコミュニケーション、ノウハウの蓄積、柔軟な対応力、そしてコストの安定性といったポイントから、内製化は企業にとって魅力的な選択と言えるでしょう。
以下では、デザイン内製の主なメリットを解説します。
スムーズなコミュニケーションが可能
デザインの内製化を導入することで、社内のデザイナーや他のメンバー同士が直接的な意思疎通を図れる環境が整い、スムーズなコミュニケーションが可能となります。同じ環境で活動しているチーム間では、意見交換やフィードバックが迅速に行えるだけでなく、デザイナー自身がプロジェクトの各段階で即座にアイデアを共有し、改善を進められる点が大きな強みです。その結果、長期的にはメンバーがお互いの専門性や役割を深く理解し、より良い成果を生み出すための基盤が形成されます。
また、外部の専門家と業務を進める場合に頻繁に発生しがちなコミュニケーションの行き違いや情報の認識違いといったリスクが、デザインの内製化を通じて大幅に軽減されます。社内でデザインプロセスを完結できるため、特にデザイナーの意図や創造性がプロジェクトにダイレクトに反映されやすくなり、クリエイティブなアプローチが促進されます。
このように、デザインの内製化による円滑なコミュニケーションは、成果物のクオリティー向上に直結し、競争力の強化にも寄与します。
ノウハウやスキルが社内に蓄積する
デザインの内製化を進めることで、企業内にデザインに関するノウハウや専門スキルが蓄積されます。これにより、デザイナーたちは日々の業務を通じて新しい技術やトレンドを学び、自身のスキルを向上させることが可能です。社員個人の成長はもちろん、チーム全体の能力強化にも寄与するため、長期的に見れば企業全体の競争力を向上させる効果があります。
社内に蓄積された知識やスキルは将来的なプロジェクトにおいて重要な資源となり、過去の成功事例や失敗から学ぶことでさらに高品質なデザインにつながります。このようなサイクルは一度構築されると継続的に機能しやすく、結果として企業の競争力を持続的に高める助けとなります。
また、「デザインの内製化」を推進することで、社内のデザイナーが中心となり、より効率的かつ一貫性のあるプロジェクト運営が可能となる点も見逃せません。
急なスケジュール変更にも対応しやすい
デザインの内製化を導入することで、急なスケジュール変更にも柔軟に対応できる環境が整います。特に社内のデザイナーは、他部署とのスムーズな連携を図りながら、変更に迅速に対応する力が備わっています。外注と比較して、内製の場合にはリソースを即座にシフトできるため、スケジュール調整の負担を最小限に抑えることが可能です。
このような迅速な対応力は、ビジネスの競争環境において重要な強みとなります。特にマーケティングやプロモーションのようなタイムリーなアクションが求められる場面では、デザインの内製化は非常に有効です。
その機動力を活かし、質の高いアイデアをその場で発展できるため、より魅力的な成果を生み出す可能性が高まります。デザイナーが内製の体制で活動することにより、スピードと創造力を兼ね備えた対応が実現するでしょう。
コストが安定しやすい
内製化の大きな利点は、コストが安定しやすい点です。デザインの内製化を進めることで、デザイナーの人件費が予測可能となり、長期的な財務計画を立てやすくなります。外部のデザイナーに依存する場合、急なコストの増加や予算オーバーといったリスクが発生することがあり、安定したコスト管理が困難となる場合があります。一方、内製化ではデザイナーの人件費が固定費として明確になるため、変動費によるコストの不安定さを解消できます。
このように、デザインの内製化を通じて固定費の安定した管理が可能になることで、企業は持続可能な成長を遂げられる基盤を構築できます。さらに、コスト環境が安定することで数値に基づいた経営判断が行いやすくなり、計画性の向上にも寄与します。デザインの内製化は、コストの安定性はもちろん、企業全体の競争力を高めることにも繋がるのです。
デザイン内製のデメリット
デザインの内製化には数多くのメリットが挙げられるものの、同時にいくつかのデメリットが存在します。
デザインの内製化を進める際には、デメリットについて十分に理解し、それに対する対策を講じておくことが求められます。
成果物の品質が担当者に依存する
デザインを内製化する際の成果物の品質は、デザイナーのスキルや経験に大きく依存します。社内のデザイナーの技術レベルが高い場合、より優れた成果物が期待できますが、スキルにばらつきが見られる場合、全体のクオリティーが低下するリスクがあります。特に新たに採用したデザイナーがプロジェクトに参加する際には、そのデザイナーが業務に慣れるまでに時間がかかり、期待通りの成果が得られない可能性も考慮する必要があります。
これを回避するためには、デザインチームの教育およびスキル向上を積極的に進めることが重要です。特に、各デザイナーの強みを活かし、特定の業務に特化させることで、より安定した高品質の成果物を生み出すことができます。また、デザイナーの成長を促進し、長期的に高いレベルのデザインを維持するためには、継続的なトレーニングやサポート体制が欠かせません。
最終的に、社内で作成されるデザインのクオリティーは、自社のブランドイメージを向上させるために不可欠な要素となります。そのため、デザイナーのスキル向上だけでなく、チーム全体で安定したクオリティーを維持する取り組みが必要です。
スキル向上に時間がかかる
デザイン業務を内製化する場合、スキル向上に時間がかかります。社内でデザイナーを育成する場合、実務経験を積むことで成長が期待できる一方、即戦力となるためには専門的な知識と技術を体系的に習得する過程が必要不可欠です。特にデザイナーにとって、実践的スキルの向上だけでなく、新たなデザイン技術や市場トレンドへの理解を深めることが求められます。
これを実現するためには、定期的なトレーニングや教育プログラムの導入が欠かせません。しかし、これには時間と労力が伴い、プロジェクトの進行を優先する場合には社内リソースの負担が増大するリスクもあるため、その点を慎重に考慮する必要があります。特に急成長中の企業やリソースが限られた環境では、この負担を軽減するための計画的な取り組みが重要です。
一方で、内製化によるスキル向上は、デザイナー自身のモチベーションを高めると同時に、企業独自のクリエイティブな文化を育むという長期的なメリットももたらします。その場合、デザイナーが成長できる環境を整備し、企業全体でその取り組みを支える戦略を構築することが不可欠です。これにより、社内で培われたデザインスキルを競争力に変えることができます。
固定費が発生する
デザインの内製化を進める際には、固定費の発生を避けることはできません。具体的には、社内にデザイナーを雇用することで、給与や福利厚生、教育費などの固定的なコストが必要です。このような固定費は、プロジェクトが少ない時期には特に経営の負担となる可能性があります。そのため、内製化を検討する際には、これらの費用を事前に十分に検討することが重要です。
固定費が短期的には負担に感じられることもありますが、長期的な視点でデザインの内製化を捉えると、その価値が大きくなるケースも少なくありません。従って、デザイナーの雇用を含む経費を一時的な負担と見るのではなく、企業の成長戦略の一環として位置付けることが重要です。内製化を成功させるためには、固定費やメリットのバランスを慎重に分析し、自社の戦略やニーズに合った最適な判断を下す必要があります。
デザイナー採用・確保の難しさ
デザインの内製化を進める際、デザイナーの採用・確保は非常に大きな課題となります。特に優秀なデザイナーは市場での需要が高く、競争が激化しているため、スキルや経験を備えた人材を採用するハードルが高いのが現状です。このような市場環境において、適切なデザインスキルを持つ人材を見つけ出すには、徹底した採用プロセスが求められます。また、デザイナーのスキル向上や成長を促す効果的な育成を実現するためには、企業のリソースを十分に確保する必要があります。
さらに、デザインの内製化には、人材の定着という重要な課題も伴います。有能なデザイナーほど他社からのオファーを受ける機会も多く、離職が増えることで採用や育成コストの増大につながるリスクがあります。そのため、競争力のある職場環境やキャリアプランを提示し、デザイナーが継続的に働きたいと感じられる仕組みを整えることが不可欠です。
企業がデザインの内製化を成功させるためには採用計画だけでなく、長期的な視点での育成および定着の具体的な目標を設定して進めることが重要です デザインの内製化を成功させるためには採用計画だけでなく、長期的な視点での育成および定着の具体的な目標を設定して進めることが重要となります。
外注と内製で迷った際の判断ポイント
デザインの外注と内製化を選択する際には、いくつかの重要な判断ポイントを考慮する必要があります。
コストをどう考えるか
コストを考える際には、デザイナーの採用や教育、設備投資など、デザインの内製化における費用構造を明確に理解することが重要です。内製化では初期投資として一定の固定費が発生しますが、社内でノウハウが蓄積されることで、長期的な視点から見ると継続的なプロジェクトにおけるコスト削減が期待できます。デザインの内製化によって、社内の意思決定がスムーズになり、素早く対応できるというメリットも得られます。
一方、デザイン業務を外注化する場合、必要なタイミングでサービスを利用できるため、柔軟なコスト管理が可能です。ただし、デザイナーの熟練度やプロジェクト規模によっては、予想を超えるコストが発生するリスクも伴います。そのため、外注化を選択する際には、品質や費用対効果を慎重に検討することが肝要です。
内製化と外注化のどちらが企業にとって効果的であるかは、業務内容や事業目標、長期的な戦略によって異なります。いずれの場合も、デザインへの投資が効率的かつ価値のあるものとなるよう、コストと各選択肢のバランスを見極める必要があります。
納期に求める柔軟性
納期の柔軟性は、デザイン業務の内製化と外注化を検討する際に非常に重要な要素となります。外注の場合、外部デザイナーとのスケジュール調整が不可欠であり、この調整が急な変更や追加依頼への迅速な対応を妨げる原因となることがあります。特に、クライアントからの要望が変更された場合、タイミングによっては大幅な遅れを招くリスクが伴います。
一方、内製化を選択することで、社内のデザイナーチームとの直接的なコミュニケーションが可能となり、迅速かつ柔軟な対応が実現します。これにより、納期に対するプレッシャーを最小限に抑えつつ、成果物のクオリティーを維持しやすくなります。さらに、社内チームならではのプロジェクトを常に把握できる体制が整っているため、スケジュール変更や新たな要請にも即座に対応可能です。
デザイナーの役割がプロジェクトの進行においていかに重要かを踏まえ、柔軟な納期管理がビジネスの成功に直結することを念頭に置きましょう。
案件数と社内リソースのバランス
デザイン業務の内製化と外注化を検討する際、案件数と社内リソースのバランスを正確に見極めることが重要です。特に、社内のデザイナーが抱えきれないほど案件数が多く、割くことのできる時間に限りがある場合、外注を活用するのが効果的です。外注することで、専門的なスキルを持つデザイナーによる高品質なデザインを短期間で実現できる可能性が高まります。
一方で、社内に安定したスキルを持つデザイナーが揃っており、ブランド戦略やデザインの一貫性を重要視する場面では、内製化が適しています。ただし、社内のデザイナーリソースが不足している状況で無理に内製化を進めると、デザインの品質が低下し、企業の信頼性や評判に悪影響を与えるリスクがあります。このため、案件量の変動や社内デザイナーの能力と稼働状況を見極めながら、適切な選択を柔軟に行うことが求められます。
以下では、デザイン業務の効率低下における課題とオンラインデザインツールを活用した解決方法を紹介していますので、ご関心のある方はぜひご覧ください。
まとめ
必要なタイミングでデザインを作成したい場合や、案件ごとにデザインが変わることが多い場合は外注が向いており、社内で統一感のあるデザインを維持したい場合や、継続的かつ大量のデザインが必要な場合は内製が向いています。
内製化する際には、オンラインデザインツールを活用することで作業の効率化や生産性の向上が望めます。オンラインデザインツール「Canva」を導入すれば、十分なデザインのスキルがないノンクリエーターでも高品質なクリエイティブ制作が可能です。
SB C&Sでは、企業・団体(ビジネス)向けのCanva有料プラン(チームス、エンタープライズ)を用意しており、より魅力的なデザインを効率的に作成できます。
以下の記事では、Canvaの特長や多様な機能について詳しく解説しています。
⇒ 誰でも簡単に無料でデザイン作成が可能な「Canva」とは?使い方や基本機能、料金プラン、商用利用について解説
『Canva相談センター』では、Canva製品に精通した専門コンシェルジュが企業導入に向けた無料相談を承っております。今回ご紹介した製品の概要や、具体的な料金が気になる・もっと詳細な情報が欲しい等々ありましたら、お気軽にご相談ください。