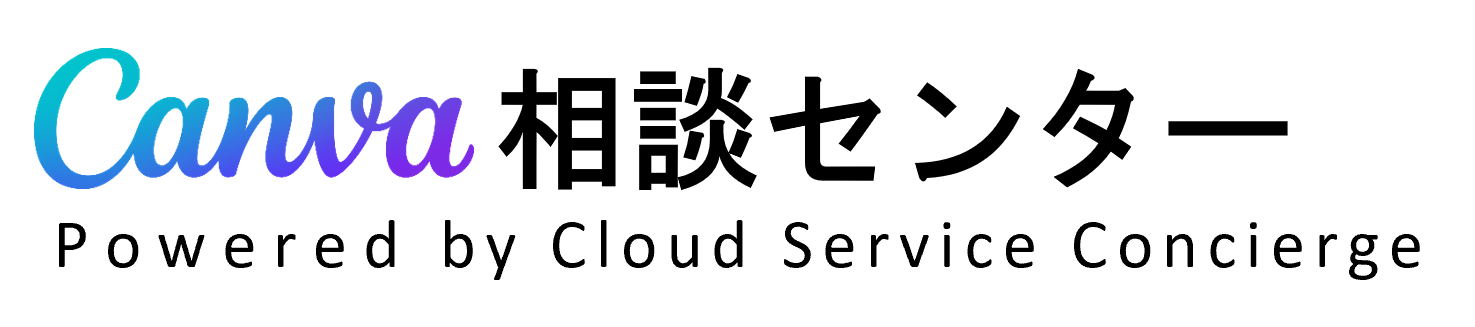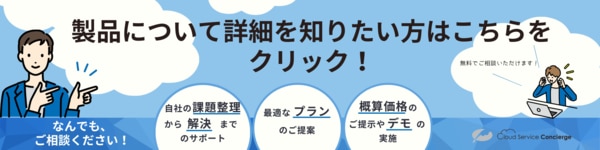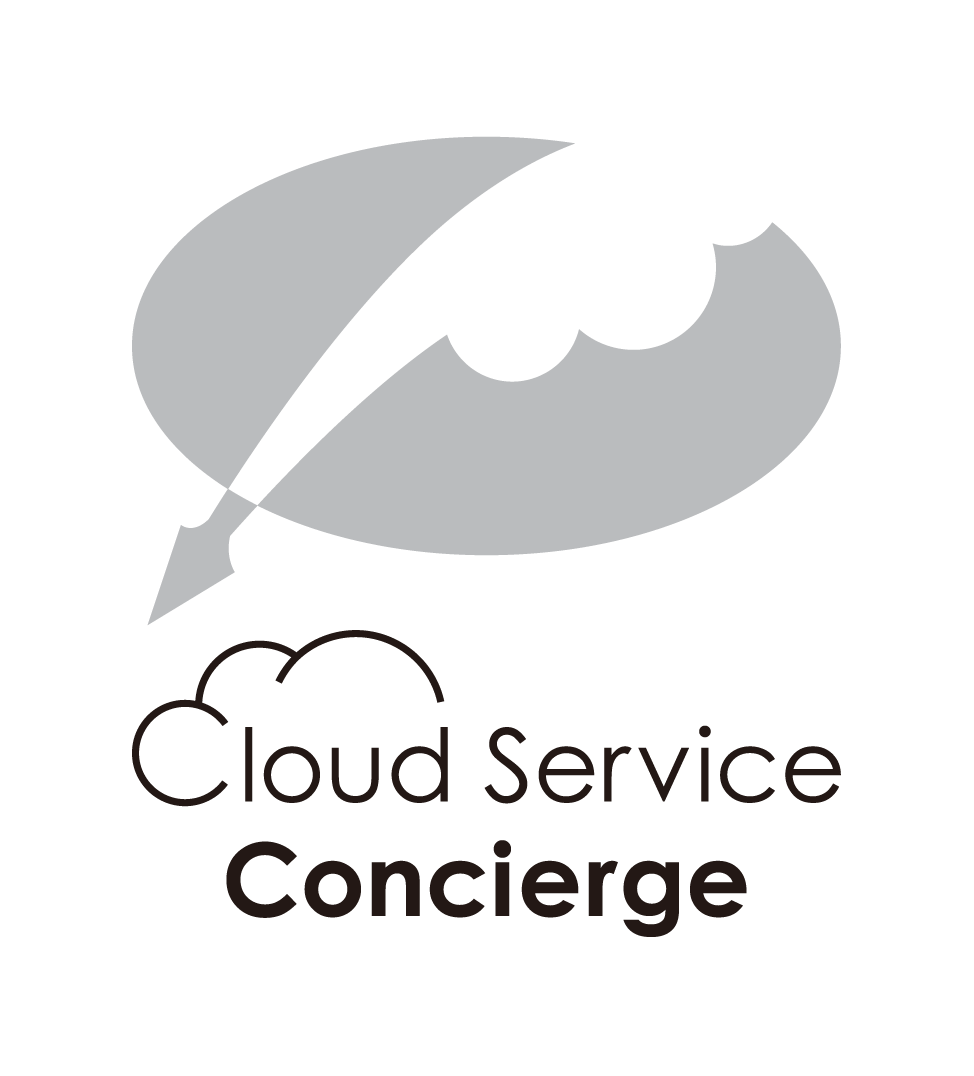資料作成におけるコツとは?企画構成とデザインの原則を解説
「プレゼン資料作成に時間がかかり他の業務への影響が出ている」、「資料作成で何から手を付けていいかわからないと悩んでいる」といった方もいるのではないでしょうか。
その状況に共通するのは、資料作成の経験がない、あるいは慣れていないということです。
この記事では、初めての方でもできる資料作成のコツ、構成とデザインの原則について解説していきます。
目次[非表示]
- 1.資料作成を始める前に知っておくべきポイント
- 1.1.資料の目的とゴールを明確にする
- 1.2.ターゲットを理解し、ニーズに応える
- 1.3.論理的な伝え方を計画する
- 2.資料作成のコツ-企画構成
- 2.1.①誰に、何を、なぜ伝えるかを設定する
- 2.2.②全体の流れを整理し、目次を作成する
- 2.3.③メッセージに根拠や説得力を加える
- 2.4.④情報を構造的に整理する
- 2.5.⑤構成をレビューして完成度を高める
- 3.資料作成のコツ‐デザインの原則
- 3.1. 一貫性を持たせるフォントと色の選び方
- 3.2.内容を際立たせるスライドの使い方
- 3.3.見やすい文字サイズと適度な余白の確保
- 3.4.図やグラフを効果的に活用する
- 3.5.シンプルな装飾と整ったレイアウト
- 4.資料作成をスムーズに進めるための手法
- 4.1.見本やテンプレートを活用する
- 4.2.ショートカットキーやツールで時短を図る
- 4.3.チームでの共同編集を活用する
- 5.まとめ
資料作成を始める前に知っておくべきポイント
資料作成を始める前にポイントを把握することは、単に作業効率を上げるだけでなく、コミュニケーションの質を高め、最終的な成果にも大きく影響する非常に重要なプロセスです。
以下では、3つのポイントを解説します。
資料の目的とゴールを明確にする
資料を作成する際の最初のステップとして、目的とゴールをはっきりと定めることが不可欠です。はじめに、その資料がどのような役割を果たし、相手にどのような行動を促したいのかを明確にする必要があります。
これはマニュアルの作成においても同様であり、読む側に具体的な手順や行動を理解させるためには、目的意識を明確に持つことが重要です。
たとえば、商品の販売促進を目的とする場合には、読み手に商品への興味を引かせ、さらに購入意欲を高める構成を意識させる必要があります。
こうした目的が明確でない場合、資料の内容が散漫になり、結果として読者を混乱させてしまう可能性があります。
さらに、資料を通じて最終的に達成したいゴールを思い描くことで、全体の方向性が定まり、内容にも一貫性が生まれます。
ゴール設定のない資料では、伝えたい情報が的確に届かない場合があります。
特にマニュアルのように、実際の行動につながる内容を提供する資料の場合、この手順や意図の明確化が伝わりやすさの鍵となります。
そのため、資料作りにおいては、まず目的を明確に定義し、そこから理想的なゴールを逆算して内容を整えていくプロセスを一貫して行うことが大切です。
ターゲットを理解し、ニーズに応える
資料作成においては、ターゲットとなる人々を深く理解することが極めて重要です。
誰に向けてその資料を作成するのかを具体的に意識することで、内容やデザインを適切に調整できます。
たとえば、経営者に向けた1枚のプレゼンテーション資料を作成する場合、情報は簡潔で要点を絞り込む必要があります。
一方、若手社員へのトレーニング用の資料では、詳細な手順や具体例を盛り込むことで理解を深められるよう工夫する必要があります。
このように、相手が何を知りたいのか、どのような情報が役立つかをしっかり見極めることは、質の高い資料作成に欠かせません。
さらに、ターゲットの期待や関心事、バックグラウンドを考慮することで、提供する情報がより説得力を持ち、共感を呼び起こす資料が実現できます。
1枚の資料であっても、その要素がターゲットのニーズに的確に応えていると、大きな影響を生むことがあります。
効果的な資料作成には、ターゲットのニーズを最優先に考え、それに合ったアプローチを取ることが鍵となります。
論理的な伝え方を計画する
情報を効果的に伝えるためには、論理的な構成と順序が重要です。
伝えたいメッセージを整理し、どのように展開するかを計画することが求められます。
まず、主題を明確に設定し、それを支持する理由や具体的なデータを慎重に用意します。
そして、情報の掲載順序を決めることとなりますが、例えば結論を先に提示し、その後に理由や裏付けとなる情報を順序立てて提示する方法があります。
最も重要なポイントを冒頭に配置することで聴衆の理解を深めるだけでなく、注目を引きつける効果も期待できます。
このように、論理的な流れと明確な順序を持つ表現によって、資料やプレゼンテーションは一層の説得力を持ち、読み手や聞き手に確かな印象を残すことができます。
資料作成のコツ-企画構成
資料の企画構成には、明確な流れと論理的な組み立てが不可欠です。
以下では企画構成のコツをステップごとに解説します。
①誰に、何を、なぜ伝えるかを設定する
資料作成において最初に決めるべきは、誰に向けて何を伝えるのかを明確にすることです。
この段階では、ターゲットと情報の目的をはっきりさせることが求められます。
具体的には、受け手の立場や期待に配慮しながら、伝えるべき重要なメッセージを提示し、情報伝達のフローを整理します。
これにより、受け手にとってわかりやすい構成が可能となり、資料内容がより効果的に伝わります。
これが完了すれば、資料全体の方向性が確立され、制作の指針となります。
また、「何を」伝えるかを絞ることにより、本当に重要な情報に焦点を当て、一貫したメッセージを発信することが可能になります。
このようにフローを意識した明確化が、後のプロセスに良い影響を与え、資料全体の質を向上させるでしょう。
②全体の流れを整理し、目次を作成する
次に全体の流れを考え、目次を作成することが重要です。
目次を適切に整理し、リスト形式で構築することで、どのような順序で情報を提示すれば良いかを明確にできます。
この段階では、先に設定した「誰に、何を、なぜ」を念頭に置き、納得できる論理的な流れを目指します。
具体的には、各セクションの内容がどのように有機的に連携するかを検討し、リストを活用してわかりやすく整理することに注力します。
さらに、目次を基盤にして資料の設計図を作成することで、後の構成作業が一層スムーズになります。
全体の視点を常に意識し、情報を整理する際もリスト形式や箇条書きを活用し、構造化することを心がけるとより効果的です。
③メッセージに根拠や説得力を加える
資料の説得力を増すためには、主張を裏付ける根拠が不可欠です。
単に結論を述べるだけでなく、その裏付けとして具体的なデータや事例を提示することが重要です。
たとえば、提案するアイデアのメリットを根拠づける際、実績データや以前の成功事例を引用することで、受け手に信頼性を提供できます。
説得力を高めるためには、メッセージを論理的に構成した上で、PREP法(Point・Reason・Example・Point)といった手法を活用するのも効果的です。
この手法では、主張、理由、具体例、再度の主張を組み合わせることで、受け手の理解を深めることが可能です。
さらに、文章の中で句読点の使い方や配置に注意することも、伝えたい内容を明確にし、メッセージをより分かりやすく伝える上で重要です。
整理された構造や正確な表現を用いることで、説得力のある資料作成が実現します。
④情報を構造的に整理する
情報を効率的に伝えるためには、構造的な整理が不可欠です。
このプロセスを進める際には、明確な手順に基づいて情報を整理することが重要です。
各見出しに沿って情報をピラミッド型に階層化することで、論理の流れが明確になります。
最上位には要点を配置し、その下に詳細情報や補足を整然と配置する方法を採用しましょう。その際には、粒度を揃えること、情報のバランスを保つことを意識する必要があります。
このように整理された情報は、読み手にとって論理的な展開が理解しやすくなるだけでなく、重要なメッセージを確実に伝えるための効果的な手段となります。
⑤構成をレビューして完成度を高める
構成が一通り整ったら、次はレビューを行います。
この段階では、第三者の意見を活用することで、自身では気づかなかった課題を明らかにできます。
情報の抜け漏れや重複、そして論理的な矛盾がないかを確認することが重要です。
また、視点を変えて資料全体を改めて見直すことで、さらなる改善の余地を探ることができます。
このような工程を通じて、資料の完成度を大幅に高めることが可能となり、コンテンツの信頼性が増し、最終的には質の向上が実現します。
レビューは、構成を仕上げるための効果的なプロセスであり、指摘されたことをしっかり意識して修正していくことが大切です。
資料作成のコツ‐デザインの原則
相手に伝わりやすい資料を作成するには、企画構成だけでなくデザインも重要です。
デザインの基本原則を理解し、それを忠実に実践することが鍵となります。
以下では、効果的なデザインの基本原則を解説します。
一貫性を持たせるフォントと色の選び方
デザインにおける一貫性は、視覚的にまとまりのある印象を与えるだけでなく、見やすさや伝わりやすさにも大きな影響を及ぼします。
フォントや色を選定する際には、資料全体を通じて統一することが重要です。
たとえば、特定のフォントを選び、1枚のスライドから次のスライドまで一貫して使用することで、読み手は内容に集中しやすくなります。
また、色に関しても、最初に基準となるカラーパレットを設定することで、資料全体に統一感を持たせることができます。
特に強調したいポイントにはアクセントカラーを活用することで、視覚的な効果を高めると同時に全体の調和を保つことが可能です。
これらの工夫により、一貫性のあるデザインが実現し、1枚1枚のスライドが洗練され、より効果的な資料を作れるようになります。
内容を際立たせるスライドの使い方
スライドの内容を際立たせるためには、各スライドに対して一つのメッセージを伝えることが肝心です。
複数の情報を一つのスライドに詰め込むと、逆に内容が散漫になり、重要なポイントが埋もれてしまうことがあります。
視覚的にシンプルなデザインを採用し、関連する情報を分けながら提示することで、聴衆の理解を深める効果が期待できます。
また、適切な画像や図を活用することで、視覚的な印象を与え、記憶に残りやすくなります。
この工夫によって、一つひとつのスライドが強力なメッセージを届けられるようになります。
見やすい文字サイズと適度な余白の確保
資料作成において、文字サイズは非常に重要な要素です。
適切な文字サイズを選ぶことで資料の視認性が向上し、受け手にとって情報を理解しやすい資料となります。
特にプレゼンテーション資料では、18ポイント以上の文字サイズを使用することが推奨されており、読み手の視認性を確保するための重要な注意点となります。
さらに、文字間や行間を適切に調整し、十分な余白を確保することも忘れてはいけません。
この余白によって情報が詰まりすぎることを防ぎ、全体の読みやすさや整理された印象を与えることができます。
資料全体のデザインはシンプルで清潔感を持たせることを意識しつつ、視認性と読みやすさを両立するよう工夫することが、効果的な資料作成のポイントとして挙げられます。
文字サイズの設定や余白のバランスなど、これらの注意点を踏まえることで、伝わりやすい資料を作成することが可能です。
図やグラフを効果的に活用する
図やグラフは、データや数字を視覚的に伝えるための強力なツールです。
具体的な数値を示す際に、視覚的に理解しやすい形で表現することで、聴衆の興味を引きやすくなります。
たとえば、棒グラフや円グラフを用いることで、類似データの比較や構成比を簡潔に伝えることが可能です。
さらに、フローを取り入れた図解を活用することで、情報の流れやプロセスをわかりやすく説明できます。
これにより、複雑な手順や関係性も直感的に理解しやすくなります。
また、イラストやアイコンを活用することで、難しい内容もイメージで理解させることができます。
情報の視覚的な表現を工夫することで、視聴者の関心を引き、記憶に残る印象を与えることができるでしょう。
シンプルな装飾と整ったレイアウト
シンプルな装飾は資料の洗練さを引き立てつつ、情報を的確に伝える助けになります。
過剰な装飾はかえって情報の伝達を妨げる可能性があるため、控えめなデザインを取り入れることが重要です。
整ったレイアウトを実現するためには、見出しや本文、画像を適切に配置し、情報を自然な流れで展開させる工夫が求められます。
また、適度なスペースを使用することで読み手が情報を整理しやすくなります。
具体的には、同じスタイルのボックスやラインを使用して統一感を持たせたり、一定の間隔を意識して配置を整えたりすることで、全体のデザインにまとまりを持たせることができます。また、リスト形式を取り入れることで、情報の要点を簡潔かつ視覚的に分かりやすく伝えることが可能です。
こうした工夫により、資料全体がシンプルでありながら説得力を持ち、読み手に印象づけられる内容を作り上げることができます。
以下の記事では、資料作成を効率化する6つのコツを紹介について詳しく解説しています。
⇒ 資料作成に時間がかかる原因と資料作成を効率化する6つのコツを紹介
資料作成をスムーズに進めるための手法
以下では、資料作成をスムーズに進めるための手法を解説します。
見本やテンプレートを活用する
資料作成の効率化を図るためには、見本やテンプレートを活用することが非常に有効です。
既存のテンプレートを利用することで、書式やレイアウトに悩む時間を大幅に減らし、迅速かつ効果的に資料を作成できます。
特にパワーポイントやワードなどのオフィスソフトには、1枚目のスライドやページに適したテンプレートが豊富に揃っており、伝えたいメッセージを的確に整理できます。
これらを使うことで、ビジュアル面のクオリティを保ちながら、見る人にとって分かりやすい資料をスピーディに仕上げることが可能です。
さらに、自分自身でカスタマイズしたテンプレートを作成し、それを繰り返し使用することで、独自のスタイルを確立できます。
1枚ごとのデザインや構成に統一感を持たせることで、プロフェッショナルな印象を与えることができ、プレゼンテーションや会議、提案資料などでの効果を高めることができます。
このように、時間の節約だけでなく、一定のクオリティを維持しながら資料を作るためにも、テンプレートの活用はとても効果的であり、仕事の効率化に欠かせないツールと言えます。
また、オンラインデザインツールには、商用利用可能なプロ仕様のテンプレートが豊富にあるため、資料作成の効率化を図るにはこのようなツールの活用も役立ちます。
以下では、オンラインデザインツールCanvaについて詳しく説明しています。
Canvaとは?特徴やできることなど基本情報をわかりやすく解説
ショートカットキーやツールで時短を図る
資料作成における効率化には、ショートカットキーや専用ツールの活用が欠かせません。
多くのソフトウェアには、日常的に使用する機能へ瞬時にアクセスできるショートカットキーが設定されています。
これを活用すれば、マウス操作の回数を減らし、作業フローを効率化しながら、スピーディに進めることが可能です。
また、デザインや図形作成に特化したツールを導入することで、短時間でプロフェッショナルな仕上がりの資料を作成できます。
これらの工夫を取り入れると、単に作業時間を短縮するだけでなく、一貫した作業フローを維持しやすくなり、集中力の維持や向上に寄与します。
チームでの共同編集を活用する
チームでの共同編集は、効率的な資料作成において非常に効果的な手法です。
複数のメンバーが同時に作業することで、情報を共有しながらスピーディに進めることが可能です。
この際、作業の順序をチーム内で明確化しておくことで、作業効率がさらに向上し、混乱を防ぐことができます。
オンラインツールやクラウドサービスを利用することで、リアルタイムでの編集やコメントのやり取りができ、意見を集約する時間を短縮できます。
また、それぞれの作業プロセスに順序立てて取り組むことで、チーム全体の生産性を高めることが期待できます。
さらに、各メンバーの専門性を生かして内容の充実度を向上させることも可能です。
このような共同作業が促進されれば、コミュニケーションも円滑になり、効率的で質の高い資料を作成できます。
▼あわせて読みたい
【徹底比較】AIで資料作成を自動化する!スライド生成AIツール4選
まとめ
資料作成においては、目的とターゲット層を意識し、論理的な構成と分かりやすいデザインを心がけることが重要です。
オンラインデザインツールの活用も、資料作成の効率化に大きく貢献します。
オンラインデザインツール「Canva」なら、無料版では200万点以上のテンプレート、有料版では450万点以上のテンプレートから目的にあった資料テンプレートを見つけることが可能です。
また、有料版のチームス、エンタープライズであれば、チーム、組織内での共有、共同編集を簡単に行うことができ、資料作成のさらなる効率化を実現します。
「Cloud Service Concierge」では、 オンラインデザインツールCanva有料版であるCanvaチームス、Canvaエンタープライズを取り扱っています。
Canvaチームス、Canvaエンタープライズはビジネスプランとして多くの企業に利用されており、無料版やCanvaプロよりも⾼度な機能、セキュリティ・管理で企業の働き⽅のリデザインを実現します。
\Canvaの製品詳細&資料DLはこちら/
『Canva相談センター』では、Canva製品に精通した専門コンシェルジュが導入に向けた無料相談を承っております。
ビジネス版Canva導入をご検討中の担当者さまはお気軽にご相談ください。