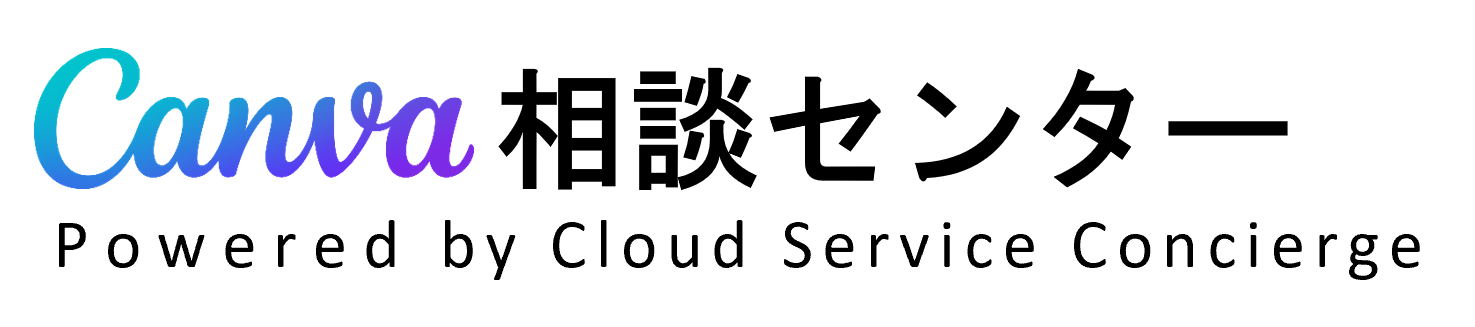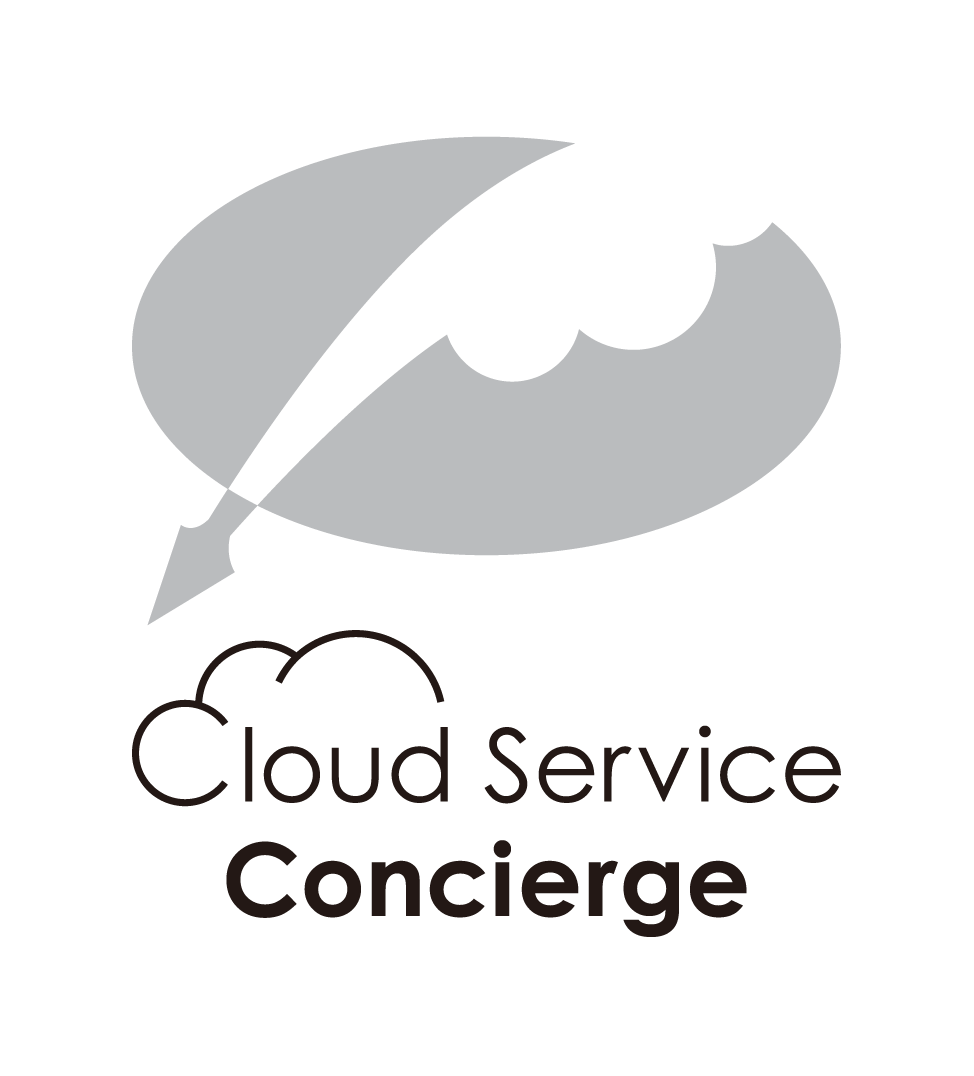担当者必見!見る人を惹きつける会社紹介資料の極意とポイント
会社紹介資料は、企業の信頼性や魅力を伝えるうえで欠かせない存在です。商談や採用、パートナーシップの場など、多くのビジネスシーンにおいて第一印象を左右する大切なツールです。資料の完成度が企業のイメージや成果に直結するからこそ、戦略的かつ効果的に作り込むことが求められます。
本記事では、成果の出る会社紹介資料を作成するための基本から実践ポイントまでを体系的に解説します。
目次[非表示]
成果を出す会社紹介資料の目的と種類
会社紹介資料は単なる説明ツールではなく、相手に印象を残しながら、行動を促す戦略的なコミュニケーション手段です。用途やターゲットに応じて伝える情報や構成も異なるため、目的に即した資料を用意することが成果を左右します。
この章では、会社紹介資料の基本的な役割と活用シーンについて整理し、適切な資料作りの基本的考え方を解説します。
会社紹介資料の重要性とは
会社紹介資料は、企業にとって最初に相手と接する場であり、その第一印象を左右するため重要です。また、営業活動では信頼を得るための根拠として、採用活動では求職者に企業文化を伝えるきっかけにもなります。
このように、会社紹介資料は、企業が「どのような存在であるか」を相手に分かりやすく伝える役割を担っています。そのため、資料の内容や表現方法はとても大切です。言い換えると、資料の構成や見せ方を工夫することで、相手の理解や印象が変わる可能性もあります。
目的別 会社紹介資料の種類と活用シーン
【目的別会社紹介資料比較表】
会社紹介資料には、上記表のように営業用・採用用・IR用など、目的ごとに最適な内容と構成があります。営業資料であれば事業内容や実績、顧客事例を中心に組み立て、採用資料では理念や社風、働く社員の姿などが紹介されます。また、IR資料では財務データや将来の展望が重要となるため、使用シーンに応じた取捨選択が必要です。
さらに、同じ目的の資料であっても、配布対象や活用場面によって、ページ構成やビジュアル設計に変化を持たせることが有効です。例えば、印刷用の冊子タイプと画面共有用のスライドタイプでは、伝え方や情報の量も異なってくるため、それぞれに適した設計が必要になります。それぞれの目的にあわせて訴求力のある会社紹介資料を作成することが、成果につながる第一歩です。
見た目や構成で変わる会社紹介資料の形式パターン
会社紹介資料は、目的だけでなく「見せ方」や「構成方法」にも複数の形式があります。以下に表をまとめました。
【形式別会社紹介資料の種類】
※これ以外にも形式はあります。上記は代表例です。
冊子やパンフレット状の資料は、対面営業や合同説明会などで一括配布する用途に向いており、視認性や一覧性がメリットです。また、スライド型の資料はオンライン商談や説明会での画面共有に適しており、1枚ごとの訴求力やテンポの良さがあります。さらに、差し込み型の構成を採用することで、固定部分と可変部分を分けておき、商談相手や目的に応じた柔軟なカスタマイズが可能です。
企業によっては、営業用・採用用・IR用・取引先用などの目的ごとに最初から別立てで用意されているケースもあり、汎用型資料と目的特化型資料を使い分けることもあります。このように、見た目や構成の設計も成果に直結する要素となるため、会社紹介資料作成の段階で戦略的に計画することが重要です。
また、以下に会社紹介資料に盛り込むべき要素を整理しました。これから制作される場合の参考にしてください。
【会社紹介資料の主な構成要素】
【企画編】会社紹介資料で成果を出すための企画案
成果が出る会社紹介資料を作るには、企画段階での準備が欠かせません。資料の方向性が不明確なまま進めると、情報の取捨選択ができず、内容がぼやけてしまいます。ターゲットの明確化や競合他社分析、自社の強みの言語化といった基礎設計を行うことで、相手に届くメッセージを練り上げられます。
①ターゲットのニーズを特定する
会社紹介資料を作成するうえで、まず重要なのは「誰に向けて情報を届けるのか」を明確にすることです。ターゲットがあいまいなままでは、いかに見栄えのよい資料でも、内容が相手に響かず、期待する成果にはつながりません。
ターゲット設定は、企業規模や業種・役職・年齢層・興味関心など、多面的に行います。営業向け資料であれば「決裁権を持つ部長クラス」「新規開拓が課題の中小企業」といった具体的なペルソナを想定することが有効です。採用向け資料であれば、職種やキャリア志向、価値観などをベースにした細やかな分類が必要です。
ここで言う「ニーズ」は、読み手側の知りたい情報・抱えている課題・感じている魅力に関する期待を指します。送り手の伝えたいことだけで構成するのではなく、受け手が「知りたい」と思う視点で内容を組み立てることで、会社紹介資料の訴求力が高まります。
②会社紹介資料の明確な目的設定とゴール
会社紹介資料を通じて達成したい「目的設定」が曖昧なままだと、資料の軸がぶれてしまい、印象に残らないものになりがちです。営業目的であれば商談の促進、採用目的であれば応募促進、IRであれば投資家への理解促進など、目的によって掲載すべき情報やトーンが異なります。
前章でお伝えしたように、会社紹介資料の構成方針には2つの考え方があります。ひとつは「汎用的な基本資料」をベースにしながら、必要に応じてセクションを差し替えて使い回す方式です。もうひとつは、最初から目的に特化した資料を個別に設計する方法で、訴求の精度がより正確になります。
どちらの方式を採用するかは、対象者の属性や活用シーン、社内リソースなどに応じて判断することが大切です。いずれにしても、最終的にどのような成果を得たいのかという「ゴール」を定めることで、内容の取捨選択やメッセージの設計が明確になり、相手に伝わる資料へと近づけます。
③競合他社分析と自社の強みUSPの言語化
魅力的な資料を作るためには、競合他社との違いを明確にする必要があります。そのためにまず行うべきは、競合他社の会社紹介資料の分析です。構成やデザイン、メッセージのトーン、使用されている表現方法などを比較することで、自社との違いや業界内での自社のポジションが客観的に見えてきます。
次に、自社が持つ独自の価値であるUSP(Unique Selling Proposition)※1を整理し、分かりやすく表現します。これは「自社ならではの価値提案」を整理・言語化することで、競合他社と差別化する方法です。例えば、「業界最速の対応力」「地域密着型のサポート」「独自の技術力」といったコピーにより、顧客にとっての明確なベネフィットを伝えられるように設計します。
抽象的な表現ではなく、数字や実績、事例を交えて具体的に表現することで、会社紹介資料全体の説得力が高まります。
※1 USP(Unique Selling Proposition):競合製品にはない、自社の商品やサービスが持つ独自の特徴や顧客への提供価値を意味するマーケティング用語のこと。
④成功事例から学ぶ 企画段階で押さえるべきポイント
効果的な会社紹介資料を作るには、前述でお伝えしたように、競合他社の成功事例から学ぶ姿勢も大切です。特に成果につながっている企業の資料には、ターゲットの共感を引き出すストーリー構成や、視認性のよいデザイン・メッセージの明瞭さなど、共通する工夫が施されています。例えば、実績をただ並べるのではなく、インフォグラフィックやチャートを用いて印象的に見せていたり、社員の声を取り入れて企業文化を具体的に伝えていたりする事例もあります。
こうした優れた要素を取り入れる際は、単なる模倣にとどまらず、自社の目的やブランドイメージ、企業文化と照らしあわせてカスタマイズすることが重要です。目的に合致した構成・表現に昇華させることで、資料の完成度と訴求力を一層高められます。
【構成編】魅力的な会社紹介資料の骨子を作る
伝えるべき情報を正しく整理し、順を追って提示することが、資料の構成力です。読者が自然と読み進めたくなるような流れを意識しながら、企業としての魅力を論理的かつ感情的に伝えるストーリーを組み立てる必要があります。この章では、読まれる資料の構成要素とメッセージの工夫について解説します。
①読み手を惹きつける会社紹介資料の構成要素と流れ
読み手にとって、会社紹介資料の最初の数ページは企業の印象を左右します。会社紹介資料でまず演出したいのが、以下の4点です。
信頼性を高める会社概要
読み手(これから資料を読む方)の課題や業界現状
自社製品・サービス紹介
共感性や安心感を示す実績・今後の展望
※4つのポイントはゼロから作成する場合を想定しています。
例えば、冒頭に「会社概要」「ビジョン」「ミッション」を配置し、その後に資料を渡された側の課題や自社が所属する業界の現状を表示します。これを入れることにより、より読み手が自分や自社の課題と重ねて感じ取ることが可能です。
そして次に「主力事業」や「サービスの紹介」を表示し、最後に「導入実績」「顧客の声」などを展開する構成が効果的です。段階を追いつつ情報を開示することで、相手の理解と納得を促せます。さらに、終盤に「未来の展望」や「問い合わせ先」「資料請求の案内」を配置すれば、行動につながる導線も自然に整います。目的に応じて構成の順番を調整する柔軟さも重要です。
②ストーリーで伝えるメッセージ設計のコツ
会社紹介資料は、単なる事実の羅列ではなく、「どのような想いで」「なぜこの事業を展開しているのか」といった背景を伝えるストーリー性が必要です。例えば創業者の体験談や、企業が直面した危機を乗り越えたエピソードなどは、読み手の共感を得やすく、記憶にも残りやすい内容です。
数字や実績を紹介する際も、「Aという課題があり、それを解決するためにB施策を実施した結果Cの成果が出た」といったストーリー性のある文脈をつけることで、説得力が高まります。読み手の心が動く語り口を意識してください。
③データや実績を効果的に見せる表現方法
実績を伝える際は、単に「売り上げ〇〇億円」や「導入社数〇〇社」と書くだけでなく、その数字がどのような意味を持つのかを説明することが重要です。例えば、「導入社数が前年比150%に伸びた背景には、新たな市場開拓戦略があった」といった因果関係を示すと、読み手は納得感を持ちやすくなります。
さらに、折れ線グラフ・棒グラフ・円グラフなどを適切に使い分け、情報を視覚的に提示する工夫も大切です。インフォグラフィック※1を活用すれば、複雑なデータも直感的に伝えられます。
※1 インフォグラフィック:複雑な情報やデータを、図、グラフ、イラスト、地図などのデザイン要素を用いて視覚的に整理し、誰もが直感的に理解できるように伝える表現手法
④場合によっては短くまとめる・重要な部分は手厚く表現する
会社紹介資料は、読み手に理解してもらいたいために、あれこれ入れたくなるかもしれません。読み手に期待するのは、自社を理解してもらうことと製品やサービスを知って興味を持ってもらうことです。そのため、読み手側に立ち、読み手の知りたいことを短くまとめることも場合によっては必要です。
例えば、商談相手が読み手の場合、次のような作り方もおすすめです。まず、目的と商談相手を考えて、構成内容を決めます。この時すでに既存の資料があれば、それをカスタマイズします。全部の情報を掲載せず割愛する部分は除き、最も訴求したい部分を少し多めに表現することも大切です。
丁寧に会社概要を伝えることも大切ですが、読み手が営業の場面で一番知りたいのは、サービス内容や製品情報・実績・導入事例ではないでしょうか。場合によっては短くまとめ、大事なところは手厚く表現するように臨機応変にカスタマイズすることが重要です。
【デザイン編】視覚で訴える会社紹介資料の作り方
資料の内容がどれだけ優れていても、デザインが見づらいと相手に伝わりません。視覚情報は第一印象を決める要素であり、文字の配置や配色、フォントの選び方ひとつで読み手の理解度が変わります。
この章では、プロの視点で考えるデザイン原則と、ブランド表現につながるポイントを解説します。
①プロが実践するデザインの基本原則とレイアウト
効果的なレイアウトを実現するためには、「近接」「整列」「対比」「反復」という4つの基本原則を押さえることが不可欠です。以下はその4つの原則です。
近接:関連性のある要素をグループとして近くに配置する
整列:要素を意図的に配置し、ページ全体に統一感を出す
対比:要素の大きさや色を変えて違いを強調する
反復:フォントスタイル、色、形を繰り返し使いデザインの一貫性を出す
このような基本原則を活用すると、情報伝達が向上するだけでなく、デザインに一貫性が出ることでプロフェッショナルな印象を与えることが可能です。また、対比の原則を用いることで、読み手の注意を引き、メッセージが伝わりやすくなります。
例えば、タイトルと本文を左揃えで統一する、各セクションに十分な余白を持たせるといった細かい調整だけで読みやすさが向上します。重要な情報には強調色や太字を使い、読者の視線を誘導する設計も重要です。また、レイアウトが各ページでバラバラだと統一感が損なわれてしまうため、全体のトーン&マナーをそろえるように意識してください。
②ブランドイメージを伝える配色とフォントの選び方
配色やフォントは、企業の個性や信頼性を視覚的に伝えるための重要な要素です。例えば、金融機関やコンサルティング業では落ち着いたブルー系が好まれ、クリエイティブ業界ではビビッドなアクセントカラーが用いられることもあります。
フォントも同様に、堅実な印象を与えたいなら明朝体、親しみやすさを出したいなら丸ゴシックなど、用途に応じて使い分けると効果的です。ブランドガイドライン※2がある場合は、それに従うことで一貫性を保てます。
※2 ブランドガイドライン:ブランドのロゴ、色、フォント、文体などの要素の使用ルールをまとめたブランドの取扱説明書のこと。
③インフォグラフィックや画像を効果的に活用する
情報をより直感的に伝えるには、インフォグラフィックやアイコン、図解の活用が効果的です。例えば「成長率」や「売り上げ構成比」などのデータは、テキストよりも図表のほうが伝わりやすく、視覚的にもインパクトがあります。
また、実際の製品写真や社員の笑顔写真など、企業らしさを表現できる画像も資料の説得力を高める要素です。ただし、画像やイラストを多用しすぎると情報が散漫になるため、全体のバランスを見ながら配置することが求められます。
④人気企業の会社紹介資料に学ぶデザイン術
先進的な企業が制作している会社紹介資料には、洗練されたデザインのヒントが数多く詰まっています。例えば、1ページに情報を詰め込みすぎず、空白を活かした見せ方が採用されている資料は、読みやすさと高級感を両立させています。
また、図版や文字サイズの調整により、読者の視線を誘導する技術も参考になります。実際に有名企業の資料を収集・分析することで、自社に応用できるアイデアが見つかるはずです。こうした工夫を取り入れることで格段に見栄えのする資料に仕上げることが可能です。
【実践編】会社紹介資料の運用と改善サイクル
会社紹介資料は一度作成して終わりというわけではなく、運用フェーズでの反応を確認しながら、継続的に改善を重ねることが大切です。時代や市場環境が変化すれば、伝えるべき内容やフォーカスすべきポイントも変わります
この章では、会社紹介資料の実際の運用方法や改善サイクルの回し方について解説します。
①資料公開後の効果測定とフィードバックの活用
資料を配布・公開したあとは、どの程度活用され、どのような成果につながっているかを必ず把握することが大切です。例えば、会社紹介資料がオンラインに掲載されている場合、ダウンロード数や滞在時間、スライドの閲覧完了率といった数値が参考になります。
営業シーンで使用した場合は、資料提出後の反応も重要な指標です。また、実際に会社紹介資料を使った現場担当者や顧客からのフィードバックを集めることで、修正すべき箇所や加えるべき情報が明確になります。定期的なレビュー体制を整えておくことが、会社紹介資料の精度を高める近道です。
②A/Bテストで会社紹介資料をブラッシュアップする
会社紹介資料は改善の余地を見つけやすいドキュメントです。資料をオンラインで公開し、ユーザーの反応や行動(問い合わせ)を測定したいこともあります。A/Bテストは、資料の目的(問い合わせ獲得や資料請求の増加など)に対して、どのパターンがより高い成果を出せるかを検証するのに役立ちます。
例えば同じ資料で「図を大きくした版」「導入事例を前半に置いた版」など、複数パターンを用意してA/Bテストを行うと、どの構成が相手に響くかが数値化できます。営業用の会社紹介資料であれば、提案後のレスポンスや次回アポイントメントの獲得率が指標です。採用用の会社資料では、応募者の属性変化や説明会での理解度も確認してみます。こうした小さなテストの積み重ねが、会社紹介資料の完成度を左右します。
最新ツールを活用した効率的な資料作成
資料作成には時間と労力がかかります。しかし、デザインや編集機能に優れたツールを使えば、効率よく高品質なアウトプットが可能です。なかでもCanvaのようなクラウド型のデザインツールは、テンプレートと直感的な操作性により、誰でも簡単に洗練された資料を作成できます。
Canvaについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
⇒ 誰でも簡単に無料でデザイン作成が可能な「Canva」とは?使い方や基本機能、料金プラン、商用利用について解説
この章では、Canvaを中心に、資料作成に役立つツールの特長を紹介します。
①Canvaを使った会社紹介資料の作成方法
Canvaは、ビジネス資料向けのテンプレートが豊富で、パワーポイントのようにゼロからデザインを考える必要がありません。テンプレートを選び、文章と画像を差し替えるだけで、視認性のよい資料が完成します。
お手持ちのロゴや素材をアップロードするか、500を超える素材集から好みのものを選ぶことが可能です。円グラフ・棒グラフ・折れ線グラフなど、20種類以上のグラフもブラウザ上で簡単に作成できます。クラウド上で保存・共有できるため、ファイル管理もスムーズです。デザイン初心者でも、魅力的な資料を手軽に作成できます。
②企画から制作まで素早く作成できるCanvaの魅力
Canvaは、単なるデザインツールではなく、企画から完成までのプロセスを一貫して支援できる点が大きな特徴です。例えば、企画初期にはホワイトボード機能※3を使って関係者とアイデアを可視化・共有し、「Canva Docs(ドキュメント機能)」※4で構成案や文案をリアルタイムに整理できます。さらに、表やグラフ機能を活用して、スプレッドシートのようにデータをまとめながら視覚的に資料へ反映することも可能です。
こうした機能を連携させることで、思考の整理・情報の蓄積・デザインの作成を一つのプラットフォームで効率よく進められます。加えて、共同編集やコメント機能もあるため、メンバー間のフィードバックもスムーズに行え、短期間で高品質な資料が完成します。
また、コメント機能や共同編集機能により、社内でリアルタイムにフィードバックを出し合えるため、複数人での資料作成にも最適です。メールのやり取りや修正ファイルの送受信といった従来の手間を省けるため、時間短縮にも貢献します。
※3 ホワイトボード機能:オンライン上で複数人が同時に共同作業できる、無限に広がるキャンバスのこと。キャンバスの大きさの制限を気にせずアイデアを広げられる。
※4 Canva Docs(Canvaドキュメント):画像、動画、グラフ、グラフィックなどのビジュアル要素を簡単に組み合わせて、デザイン性の高い文書を作成できるドキュメントエディターのこと。
▼関連記事
Canvaシート活用ガイド|業務で“伝わる表”を作る方法
Canvaホワイトボード活用術|会議をもっとスムーズにする新しいアイデア共有の形
③ブランド機能を使えば統一性のある資料作りが可能に
Canvaのブランド機能※5を活用すれば、資料の統一感と効率的なカスタマイズを両立できます。特に「ブランドキット」では、企業のロゴ、ブランドカラー、フォントなどを一元管理でき、デザイン作成時に簡単に呼び出すことが可能です。これにより、部署や担当者が異なる場合でも、資料のトーンやビジュアルにズレが生じにくくなります。
さらに、「ブランドテンプレート」として、あらかじめ用途別の資料を作成しておけば、担当者はベースデザインを崩すことなく、必要な情報だけを加筆・修正が可能です。テンプレートには、写真の配置やタイトルの位置、使用フォントなども設定できるため、短時間で高品質な資料を仕上げることができます。
これらの機能は、各プランで提供※6されており、複数のメンバーで共有・活用することで、社内のブランディング力を強化できます。資料のクオリティと一貫性を保ちながら、運用負荷を軽減できる実用性の高い機能です。
※5 ブランド機能:ブランドキットという機能で、ロゴ、ブランドカラー、フォントなどを一元管理し、デザイン作成時に簡単に呼び出して一貫性を保つことができる。
※6 ブランドキットの提供:無料ユーザーは1個のブランドキット/CanvaProプロ・チームス・エンタープライズ 共に 1,000個のブランドキットが提供されている。
▼関連記事
Canvaのブランド機能で社内デザインを統一する方法
まとめ
会社紹介資料は、企業の価値や信頼性を伝える重要なツールです。ただ見た目を整えるだけではなく、戦略的な企画・構成・デザイン・運用改善までを一貫して行うことが、成果につながる資料作成の鍵となります。
会社紹介資料を作成する際は、相手のニーズを的確に把握したうえで、目的を明確にすることが大切です。論理的な構成に加えて、共感が得られるストーリーを意識することで、より伝わる内容になります。また、デザインの工夫やデジタルツールの活用によって、完成度アップと作業効率の両立も可能です。
Canvaのような直感的で多機能なツールを導入すれば、デザイナーでない方もプロレベルの資料作成が可能になります。今後は、こうしたツールを活用しながら、自社のブランド力を伝えるための資料を戦略的に運用しましょう。
『Canva相談センター』では、Canva製品に精通した専門コンシェルジュが導入に向けた無料相談を承っております。ビジネス版Canva導入をご検討中の担当者さまはお気軽にご相談ください。