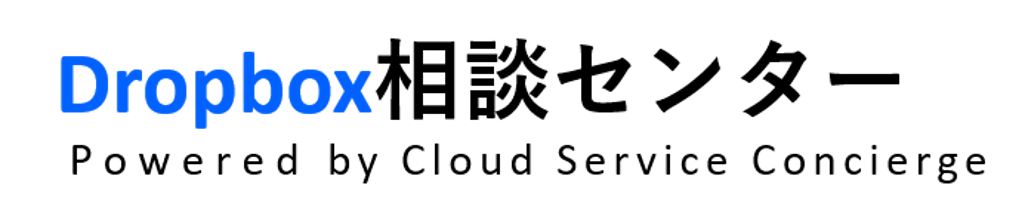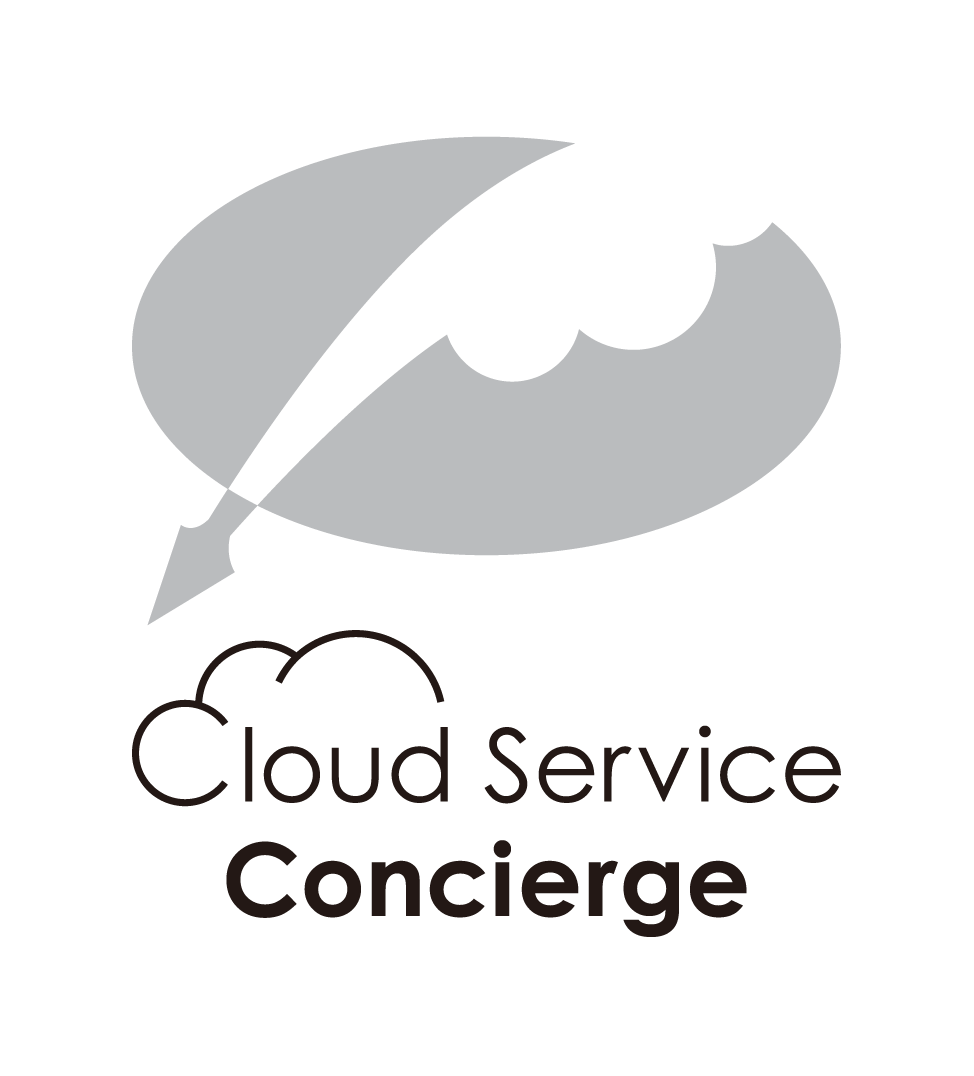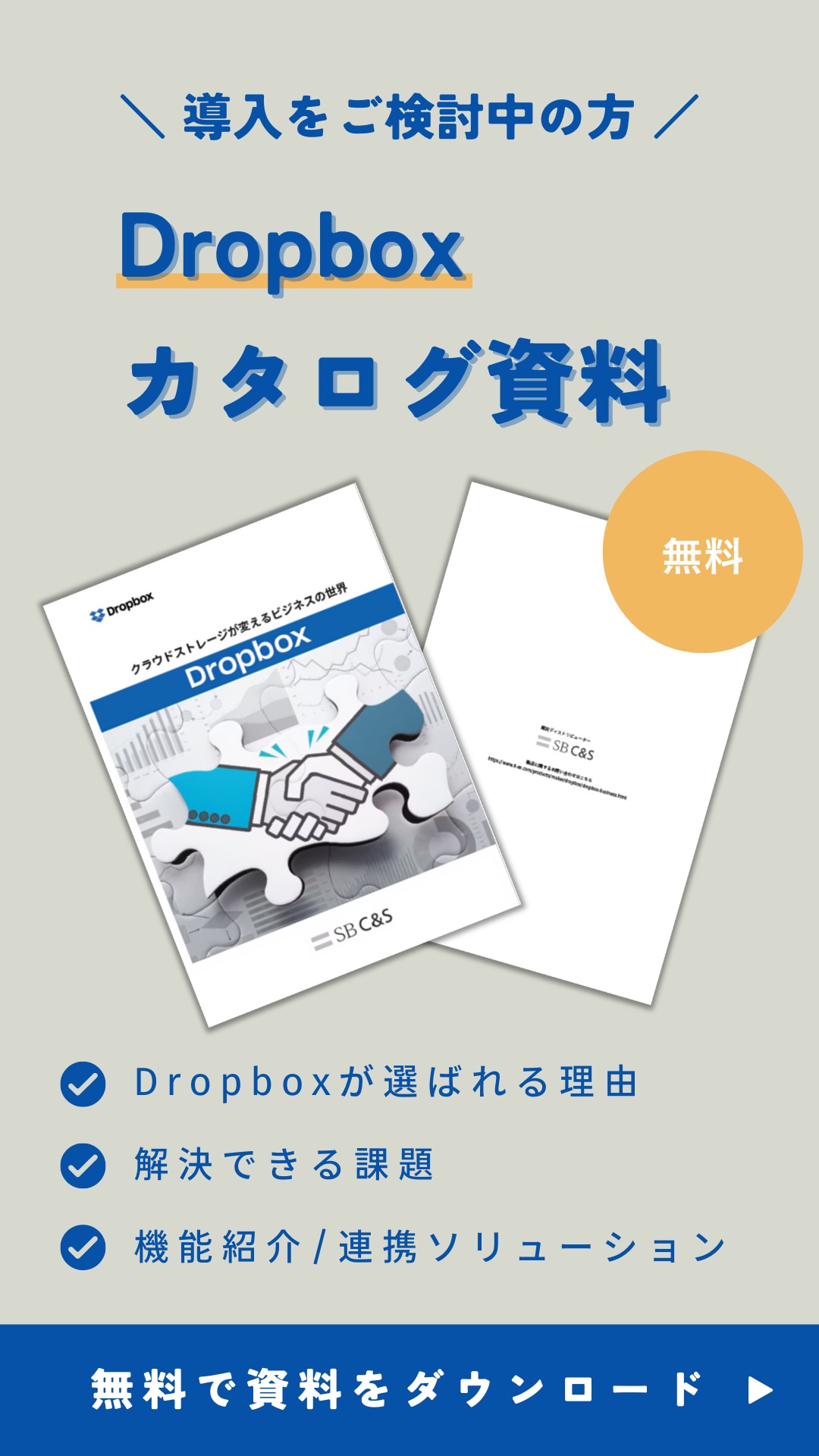研究データ管理を効率化!GakuNin RDMとDropboxの連携で研究環境が進化する(前編)
研究データの管理に悩む研究者や大学のIT担当者は多いのではないでしょうか。近年、オープンサイエンスの潮流と共に、研究データを適切に管理・共有・保存することの重要性がますます高まっています。本記事では、前編/後編に分けて、国産の研究データ管理基盤「GakuNin RDM」と、拡張ストレージとしての「Dropbox」の連携について詳しく解説します。
参考:GakuNin RDM公式サイト (国立情報学研究所)
参考:GakuNin RDM サポートポータル
目次[非表示]
・Dropboxを拡張ストレージとして活用する利点
・Dropboxの基本機能と特長
・GakuNin RDMとDropboxの連携メリット
・教育研究現場でのDropbox活用事例
・GakuNin RDMとDropboxで実現する理想的な研究環境
研究データ管理の課題と必要性
研究活動においてデータ管理が重要だと頭では理解していても、実際にどう取り組めばよいのか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。ではなぜ今、研究データ管理が注目されているのでしょうか。
増大する研究データ量への対応
近年の研究活動では、以前と比較にならないほど大量のデータが生成されています。高性能な実験装置、シミュレーション、センサー技術の発達により、一つの研究プロジェクトで数テラバイトものデータが生み出されることも珍しくありません。
例えば、ゲノム解析の分野では、次世代シーケンサーの発達により、一人の全ゲノム配列を解読するのに数百ギガバイトのデータが生成されます。このようなデータを適切に保存・管理することは、個人のハードディスクやUSBメモリではもはや対応できない状況になっています。
研究データの増大は単に容量の問題だけでなく、データの種類や形式の多様化も意味しています。テキストデータ、画像、動画、専用機器の出力ファイルなど、様々な形式のデータを統合的に管理する必要性が生じているのです。
オープンサイエンス時代の研究データ管理
「オープンサイエンス」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは研究成果や研究過程で得られたデータを広く公開・共有することで、科学の発展を加速させようという世界的な動きです。
日本でも文部科学省が2016年に「オープンサイエンス推進に関するガイドライン」を発表し、公的資金を用いた研究成果やデータの公開を推進しています。特に2022年以降、科研費などの公的研究費を受ける場合、データ管理計画(DMP: Data Management Plan)の提出が求められるようになってきました。
参考:文部科学省「オープンサイエンスの推進について」資料
参考:日本学術振興会「科研費における研究データの管理・利活用について」
このような状況下で、研究データを「いつ、誰が、どのように」生成・加工したのかという履歴を含めて適切に管理することが、研究者に求められるようになっているのです。これは単なる義務だけではなく、自身の研究の信頼性を高め、他の研究者との協力を促進するための重要なステップでもあります。
研究機関と研究者が直面する共通の悩み
研究データ管理において、研究機関と研究者はそれぞれの立場から様々な課題に直面しています。
立場 | 抱える悩み |
|---|---|
研究機関(大学や研究所)の IT担当者や管理者 | ・増大する研究データを安全に保存するためのインフラ構築コスト |
研究者や大学院生 | ・複数のプロジェクトにまたがるデータの整理・管理 |
これらの課題に対して、使いやすく、かつ機関のポリシーに準拠したデータ管理基盤が求められています。ここで登場するのが、国産の研究データ管理基盤「GakuNin RDM」です。
GakuNin RDMとは?基本概念と特徴
それでは、研究データ管理の課題を解決するツールとして注目されているGakuNin RDMについて、詳しく見ていきましょう。
GakuNin RDMの概要と開発背景
GakuNin RDM(ガクニン アールディーエム)は、国立情報学研究所(NII)が提供する研究データ管理のためのクラウドサービスです。名称の「RDM」は「Research Data Management」の略で、その名の通り研究データの管理に特化したプラットフォームとなっています。
GakuNin RDMは、NIIが推進する「オープンサイエンス基盤研究センター」のプロジェクトとして開発されました。日本の研究環境に最適化された研究データ管理基盤を構築することで、国内の研究者や研究機関がオープンサイエンス時代に対応できるよう支援することを目的としています。
特筆すべきは、GakuNin RDMが単なるストレージサービスではなく、研究ワークフロー全体をサポートする総合的な研究データ管理基盤であるという点です。データの作成から保存、共有、公開までの研究データライフサイクル全体をカバーする設計になっています。
GakuNin RDMの主要機能と特長
機能・特長 | 詳細 |
|---|---|
プロジェクト単位のデータ管理 | ◦研究プロジェクトごとに独立した作業スペースを作成可能 |
バージョン管理機能 | ◦ファイルの変更履歴を自動的に記録 ◦過去のバージョンへの復元も簡単に実行可能 |
柔軟なコラボレーション機能 | ◦機関内外の研究者との共同作業を支援 ◦きめ細かなアクセス権限設定が可能 |
メタデータ管理 | ◦データに関する説明情報(メタデータ)を付与可能 ◦将来の検索や再利用を容易にする |
学認(GakuNin)との連携 | ◦大学間連携のための学術認証フェデレーション「学認」と連携 ◦所属機関のIDとパスワードでログイン可能 |
拡張ストレージ機能 | ◦様々なクラウドストレージサービスと連携可能 ◦既存のストレージ環境を活用できる |
参考:GakuNin RDM公式サイト (国立情報学研究所)
これらの機能により、研究者は自身の研究データを効率的に管理しながら、必要に応じて他の研究者と共同作業を行うことができます。また、研究機関側も、組織として一貫した研究データ管理方針を実現しやすくなります。
GakuNin RDMの導入メリット
GakuNin RDMの導入は、各方面に様々なメリットをもたらします。
研究機関のIT担当者や管理者にとってのメリット
メリット | 詳細 |
|---|---|
コスト効率の向上 |
|
セキュリティとコンプライアンスの強化 |
|
研究データガバナンスの実現 |
|
研究支援体制の強化 |
|
特に注目すべきは、GakuNin RDMが国内の学術認証基盤である学認(GakuNin)と連携している点です。これにより、既存の認証システムとの統合がスムーズで、導入・運用の負担が軽減されます。
研究者・学生にとってのメリット
メリット | 詳細 |
|---|---|
研究効率の向上 |
|
共同研究の円滑化 |
|
データの安全な保護 |
|
研究キャリアの一貫性 |
|
若手研究者や学生にとって特に重要なのは、早い段階から適切なデータ管理習慣を身につけられる点です。これは将来のキャリア発展においても大きなアドバンテージとなります。
研究公正とデータガバナンスの向上
メリット | 詳細 |
|---|---|
研究の透明性向上 |
|
研究不正防止 |
|
知的財産管理の強化 |
|
研究データの適切な管理は、研究公正(Research Integrity)の観点からも重要です。GakuNin RDMの導入は、単なる技術的ソリューションの導入を超えて、研究文化そのものを改善する契機となり得ます。特に、研究公正や研究倫理への意識が国際的に高まる中、適切なデータ管理基盤の整備は研究機関としての責任でもあるのです。
GakuNin RDMの拡張ストレージ機能とは
拡張ストレージの基本概念
GakuNin RDMの拡張ストレージとは、システムの基本ストレージに加えて、外部のストレージサービスをGakuNin RDMに接続して利用できるようにする機能です。
基本的な仕組みとしては、GakuNin RDMのプロジェクト(研究データを管理する単位)に、外部のストレージサービスを「アドオン」として追加することで、そのストレージ上のファイルをGakuNin RDM上で参照・編集できるようになります。
この機能の最大の利点は、研究者が既に使い慣れているストレージサービスをそのまま活用できることです。新しいシステムへの移行に伴うデータの移動や、操作方法の学習コストを最小限に抑えられます。
また、研究機関側から見ても、すでに契約・導入済みのストレージサービスを有効活用できるため、コスト効率が高いという利点があります。
参考:GakuNin RDM ユーザーマニュアル「外部ストレージの追加」
GakuNin RDMでは、いくつかの外部ストレージサービスとの連携が可能ですが、なかでも国内の研究教育機関で導入実績が増えているのがDropboxです。
後編では、
・Dropboxを拡張ストレージとして活用する利点
・GakuNin RDMとDropboxの連携メリット
・教育研究現場でのDropbox活用事例
について、詳しくお伝えします。
『Dropbox相談センター』は、Dropboxのサポートサイトです。Dropboxの特徴や魅力、導入事例などをまとめているほか、専門スタッフによるすべてのDropbox製品とそのライセンスのご提案を行っています。Dropboxの導入をご検討中の方はお気軽にご相談ください。